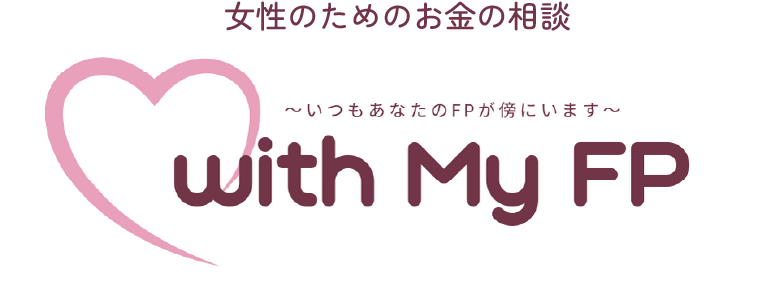2025年6月の記事一覧
【FP 大阪 最新ニュース】【返済不要の奨学金】まだまだ間に合う!2025年6月・7月締め切りの「もらえる」奨学金・2選
【返済不要の奨学金】まだまだ間に合う!2025年6月・7月締め切りの「もらえる」奨学金・2選
高等教育を希望する学生や保護者にとっては、進学にかかる費用は大きな関心事項です。 奨学金の制度を利用するか検討をする家庭も数多くあるでしょう。
続きはコチラ→https://news.yahoo.co.jp/articles/8645b3d2ece0ab5ddc584e264053709d14bcf227
【大阪 FP 最新ニュース】本は読むのに算数の文章題が解けないのはなぜ?わが子の学力を劇的に変える「教科別読み方」とは
本は読むのに算数の文章題が解けないのはなぜ?わが子の学力を劇的に変える「教科別読み方」とは
経済学者とは何ができる人間なのか。実感として私は、「経済学語をうまく話せる人が経済学者である」と考えています。
続きはコチラ→https://news.yahoo.co.jp/articles/55431503569d4e6ca0dd16c67df1ba9436b9a2c2
変動金利型住宅ローンを組んでる人必見!今後の金利上昇に備える対策とは?
近年、住宅ローンを組む多くの方が選択されている変動金利型。その背景には、長らく続いた低金利環境がありました。しかし、ここへ来て、金融政策の転換や経済状況の変化により、金利上昇の可能性が現実味を帯びてきています。
「変動金利で借りているけれど、今後金利が上がったらどうなるのだろう…」「何か事前にできる対策はあるのだろうか?」
このような不安をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は、最新の住宅ローン事情を踏まえ、変動金利型住宅ローンをご利用の方が金利上昇に備えて今からできる対策について、詳しく解説していきたいと思います!

住宅ローン金利の現状と今後の見通し
現在の日本の住宅ローン金利は、歴史的な低水準が続いています。特に変動金利型は、その低さが魅力となり、多くの方に選ばれてきました。日本銀行のマイナス金利政策解除後も、短期金利の急激な上昇は見られず、変動金利の指標となる短期プライムレートも大きく変動していません。しかし、この状況が今後も続くとは限りません。
その理由は、大きく分けて以下の2点です。
- 日本銀行の金融政策の正常化
- 海外の金利動向と経済状況
これらの要素を踏まえると、今後数年のうちに住宅ローン金利が上昇する可能性は、決して低いとは言えません。
特に変動金利型をご利用の方は、金利上昇による毎月の返済額増加のリスクに、改めて目を向ける必要があります。
変動金利型住宅ローンが抱える金利上昇リスク
変動金利型住宅ローンは、その名の通り金利が変動します。金利が下がれば返済額も減るメリットがある一方で、金利が上がれば返済額が増えるというリスクも抱えています。
多くの変動金利型住宅ローンには、「5年ルール」や「125%ルール」といった金利上昇時の返済額抑制措置が設けられています。
- 5年ルール: 金利が上昇しても、5年間は毎月の返済額が変わりません。
- 125%ルール: 5年後の返済額見直し時においても、前回の返済額の1.25倍(125%)を超える増額は行われません。
これらのルールは、急激な返済額増加を一時的に緩和してくれるものですが、注意が必要です。例えば、金利が大幅に上昇した場合、5年ルールによって毎月の返済額は据え置かれても、利息分の割合が増え、元金返済がほとんど進まない「未払い利息」が発生する可能性があります。未払い利息が発生すると、最終的なローン残高が増えてしまい、返済期間終了時もローンが残る「元金未償還」となるリスクもゼロではありません。125%ルールも同様に、増額幅に上限があるだけであり、金利が上昇し続ければ、将来的に大きな負担となる可能性を秘めているのです。
金利上昇に備える5つの対策
では、実際に金利が上昇する前に、私たちはどのような対策を講じることができるのでしょうか?
1. 資金計画の見直しと家計の点検
まずは、現在の家計状況を把握し、無理のない返済計画であるかを見直しましょう。
- 現在の収入と支出のバランス: 無駄な支出がないか、削減できる項目はないかを確認します。
- 返済負担率の確認: 住宅ローンの年間返済額が年収に占める割合(返済負担率)は、一般的に手取り年収の25%以内が目安とされています。現在の返済負担率に加え、金利が仮に1%や2%上昇した場合の返済負担率もシミュレーションしてみましょう。
- 貯蓄状況の確認: 予期せぬ金利上昇や急な出費に備え、十分な貯蓄があるかを確認します。生活費の半年分〜1年分程度の緊急予備資金を確保しておくことが理想です。
2. 繰り上げ返済の検討
手元資金に余裕がある場合は、繰り上げ返済を検討しましょう。繰り上げ返済には、「期間短縮型」と「返済額軽減型」の2種類があります。
- 期間短縮型: 毎月の返済額は変えずに、返済期間を短縮するタイプです。総返済額を最も大きく減らす効果があります。
- 返済額軽減型: 返済期間は変えずに、毎月の返済額を減らすタイプです。毎月の家計負担を軽減したい場合に有効です。
金利上昇リスクに備えるという観点では、総返済額を減らす効果の大きい期間短縮型が有効ですが、家計の状況に応じて選択しましょう。繰り上げ返済は、金利が上昇する前に元金を減らしておくことで、将来の利息負担を軽減する強力な対策となります。
3. 借り換えの検討
現在変動金利型で借り入れていて、今後の金利上昇が不安な方は、固定金利型への借り換えも選択肢の一つです。
- 固定金利型への借り換え: 全期間固定金利型や一定期間固定金利型に借り換えることで、将来の金利変動リスクを回避し、毎月の返済額を確定させることができます。金利が上昇する前に借り換えを行うことで、現在の低金利を固定できるメリットがあります。
- 借り換えの諸費用: 借り換えには、新たな金融機関への手数料や登記費用などの諸費用が発生します。これらの費用と、借り換えによるメリット(総返済額の減少や安心感)を比較検討することが重要です。
金利が上昇傾向に転じた場合、固定金利も上昇する可能性があります。借り換えを検討する際は、金融機関の担当者やFPに相談し、ご自身の状況に合った最適な選択肢を見つけるようにしましょう。
4. 金融機関への相談
住宅ローンを借り入れている金融機関に相談することも重要です。
- 金利タイプ変更の相談: 現在の変動金利型から、その金融機関内で固定金利型へ切り替えることができる場合があります。借り換えよりも手続きが簡素なケースもあります。
- 返済条件の見直し: 金利上昇によって返済が厳しくなりそうな場合、返済期間の延長や毎月の返済額の見直しなど、相談に応じてくれる可能性があります。
まずは、契約している金融機関に連絡を取り、どのような選択肢があるのかを確認してみましょう。
5. 資産運用の見直し
住宅ローンの返済とは直接関係ありませんが、家計全体で金利上昇に備えるためには、資産運用についても見直す良い機会です。
- 預貯金の活用: 金利が上昇すれば、預貯金の金利も上昇する可能性があります。普通預金や定期預金など、低リスクの預貯金で資産を確保しておくことも有効です。
- 分散投資の重要性: 株式や投資信託など、リスクのある金融商品に投資している場合は、ポートフォリオ全体を見直し、リスク分散を図りましょう。
まとめ:早めの行動が安心に繋がる
住宅ローン金利の動向は、家計に大きな影響を与えます。特に変動金利型をご利用の方は、今後の金利上昇のリスクを正しく認識し、早めに対策を講じることが何よりも重要です。
今回ご紹介した対策は、それぞれにメリット・デメリットがあります。ご自身のライフプランや家計状況に合わせて、最適な対策を選択することが大切です。
「まだ大丈夫だろう」と先送りすることなく、今からできることから着手し、安心して住宅ローンを返済できる環境を整えていきましょう。
もし、どの対策を選べば良いか迷われるようでしたら、ぜひご相談に来てください。あなたの状況に合わせた具体的なアドバイスを提供し、将来の不安を解消するお手伝いをさせていただきます。
大阪でFP相談ならwith my fp
【FP相談 大阪 最新ニュース】【貧乏になる】節約歴6年の主婦が心からやめてよかったと思う「残念な節約習慣」を5つ紹介します
【貧乏になる】節約歴6年の主婦が心からやめてよかったと思う「残念な節約習慣」を5つ紹介します
今回は、私の経験の中から、やめてよかった「残念な節約習慣」を5つ紹介します。なお、当該記事は、あくまで私の主観に基づくものであり、残念と感じるかどうかは人それぞれです。「こういう考え方もあるんだな」と気軽に読んでもらえると嬉しいです。
続きはコチラ→https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/1f1feabbf3a11d74722a43db5b2fd8d5bb16777c
【大阪 FP相談 最新ニュース】【夏のボーナスが待ち遠しい】ただし引かれる税金や社会保険料の負担に注意。昨年夏季賞与の平均は約41万円
【夏のボーナスが待ち遠しい】ただし引かれる税金や社会保険料の負担に注意。昨年夏季賞与の平均は約41万円
6月に入り、ボーナスの支給が近づくこの時期。今年4月に入社した新入社員では「初めてボーナスを受け取る」という人もいるかもしれません。
続きはコチラ→https://news.yahoo.co.jp/articles/26ad30067a989317632adfadfff9be9cfe0b091d
【FP 大阪 最新ニュース】なぜ「投資信託」には魅力的な商品がないのか…新NISAで投資家が誤解しがちな「2つの注意点」
なぜ「投資信託」には魅力的な商品がないのか…新NISAで投資家が誤解しがちな「2つの注意点」
新NISAで注目を集める投資信託。ネット上では、「儲かる」「リスクが高い」といった漠然とした的外れなイメージも先行してしまっている印象を受けます。投資信託の本当の魅力度、そして注意すべき落とし穴とは? 本記事では、シデナム慶子氏の著書『投資に必要なことはすべて海外投資家に学んだ』(サンマーク出版)より、投資信託の仕組みをわかりやすく解説します。
続きはコチラ→https://news.yahoo.co.jp/articles/26ad30067a989317632adfadfff9be9cfe0b091d
【大阪 FP 最新ニュース】夫の給料は上がったのに…妻の収入「8.8%減」の現実。家計を襲う「世帯内格差」と「コト消費」活況の裏側
夫の給料は上がったのに…妻の収入「8.8%減」の現実。家計を襲う「世帯内格差」と「コト消費」活況の裏側
家計を取り巻く環境が大きく変わるなか、収入や消費のあり方にも新たな格差が生まれています。賃上げの波が一部で広がる一方、家計の実感は必ずしも明るいものばかりではありません。今、家庭のなかで何が起きているのか。総務省『家計調査』の最新結果からその実態に迫ります。
続きはコチラ→https://news.yahoo.co.jp/articles/b163d3bc46dffff77a393cedb89ff54e5dff788d
【FP相談 大阪 最新ニュース】令和7年も「定額減税」は受けられる?「令和6年との違い」と「注意点」を解説!
令和7年も「定額減税」は受けられる?「令和6年との違い」と「注意点」を解説!
税額の負担を軽減できる制度の1つが定額減税です。令和7年も定額減税は実施されますが、令和6年に実施されたものと条件が変わっているため、注意が必要です。少しでも税金負担を少なくしたい方は、条件や減税される金額をチェックしておきましょう。
続きはコチラ→https://news.yahoo.co.jp/articles/ee3f6ac97d51aa7354fec1c3a1c640ea903c215c
【大阪 FP相談 最新ニュース】スマホ契約“しているだけ”は損かも!?意外と知られていないお得な利用方法をプロが解説
スマホ契約“しているだけ”は損かも!?意外と知られていないお得な利用方法をプロが解説
コロナ禍以降、動画配信サービスを観るようになった人も多いのではないでしょうか。その動画配信サービス、スマホのプランの特典を利用することで、より安くお得に利用できる場合があるというのを知っていますか? 節約アドバイザーの丸山晴美さんに、動画配信サービスとスマホのセットプランについて教えてもらいました。
続きはコチラ→https://news.yahoo.co.jp/articles/6fb248668acf1a0e2f8b1542c5949f289407f170
【FP 大阪 最新ニュース】【奨学金】4年間で6000万円以上支給の奨学金も!留学希望の学生必見!もらえる給付型奨学金・2選
【奨学金】4年間で6000万円以上支給の奨学金も!留学希望の学生必見!もらえる給付型奨学金・2選
高等教育を希望する学生や保護者にとっては、進学にかかる費用は大きな関心事項です。 奨学金の制度を利用するか検討をする家庭も数多くあるでしょう。
続きはコチラ→https://news.yahoo.co.jp/articles/a898bf0a852828e10322ee9b75fbaf3d52039ce5
悩む前にまずはご相談ください。
誠心誠意お応えいたします。

3営業日以内にご返信・24時間/365日受付
生活のこと、お金のことなどお気軽に
お問い合わせください。
資料もご用意しておりますのでご希望の方は
記載お願いします。
相談予約フォーム
お電話でもまずはお気軽にご連絡ください。
ご相談の概要をお聞きした上で、ご相談日を決めさせていただきます。