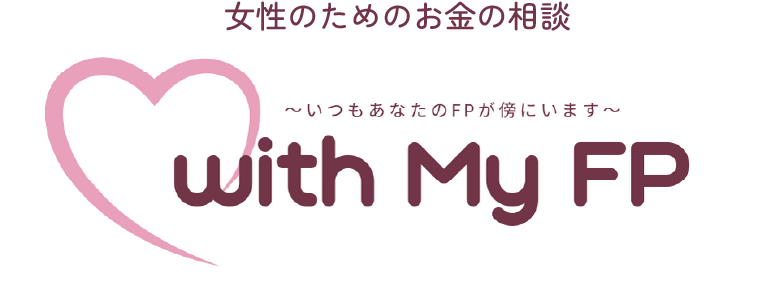「うちの子、療育が必要かも…」と悩むママへ:安心して頼れるサポートがあります
投稿日:2025.07.07
お子さまの成長に不安を感じ、「もしかしたら療育が必要なのかもしれない」と心を痛めているお母さんへ。毎日、お子さまの様子を一番近くで見ているお母さんだからこそ抱えるそのお気持ち、本当によく分かります。

「もしかして、私の育て方が悪かったのかしら?」
「この子の将来はどうなってしまうんだろう…」
そんなふうに、ご自身を責めたり、未来に不安を感じたりしていませんか? 大丈夫です。決してあなただけのせいではありませんし、一人で抱え込む必要もありません。
療育とは、お子さまの「できた!」を増やすサポート
「療育」と聞くと、特別なことのように感じたり、少し身構えてしまう方もいらっしゃるかもしれません。でも、療育とは、お子さま一人ひとりの発達の特性に合わせた「成長をサポートする手立て」のことです。
例えば、言葉の発達がゆっくりなお子さまには、遊びを通して言葉を引き出すような働きかけを。集団行動が苦手なお子さまには、お友達との関わり方を学べるような機会を。そして、手先の不器用さが気になるお子さまには、指先を使った遊びを通して巧緻性を高めるような支援を。
このように、療育はお子さまが苦手なことを克服するだけでなく、得意なことをさらに伸ばし、日常生活や社会生活での「できた!」を増やしていくための大切なプロセスです。お子さまが自信を持って、自分らしく成長していくための土台作りだと考えてみてください。
どこに相談すればいいの? 療育を受けるまでのステップ
「どこに相談したらいいのか分からない」「どんな手続きが必要なの?」といった疑問も多いかと思います。まず、最初の一歩として、いくつか相談窓口があります。
1. 市町村の窓口(障害福祉課、子育て支援課など)
お住まいの市町村には、子どもの発達に関する相談窓口が必ずあります。多くの場合、「障害福祉課」や「子育て支援課」といった名称の部署が担当しています。ここでは、専門の職員が話を聞いてくれるだけでなく、関係機関の紹介や、今後の手続きの流れなどを詳しく教えてくれます。まずは、電話で問い合わせてみたり、直接足を運んでみたりすることをおすすめします。
2. 児童発達支援センター・発達障害者支援センター
専門的な相談や支援を行っているのが、児童発達支援センターや発達障害者支援センターです。ここでは、臨床心理士や言語聴覚士、作業療法士などの専門家が、お子さまの発達の評価を行い、具体的な支援計画を立ててくれます。早期に専門的なアドバイスを受けたい場合に有効です。
3. かかりつけの小児科医
日頃からお子さまの健康状態を見ている小児科医に相談してみるのも良いでしょう。小児科医は、お子さまの発達状況を把握しており、必要であれば専門機関への紹介状を書いてくれることもあります。
療育を受けるまでの一般的な流れ
-
相談・問診: まずは、上記の窓口に相談し、お子さまの様子や気になることを伝えます。
-
発達検査・評価: 専門機関で、お子さまの発達の状況を詳しく検査・評価します。これにより、お子さまの得意なことや苦手なこと、必要な支援が見えてきます。
-
受給者証の申請: 療育を受けるためには、市町村から「通所受給者証」というものが発行される必要があります。これは、療育サービスの利用料の9割が自治体から給付されるための大切な証です。窓口で申請方法を教えてくれます。
-
支援計画の作成・サービス利用開始: 受給者証が発行されたら、お子さまに合った療育施設を選び、個別の支援計画(個別支援計画)を作成します。この計画に基づいて、療育サービスの利用が始まります。
利用できる支援サービスにはどんなものがあるの?
療育には、さまざまな形があります。お子さまのニーズや状況に合わせて、利用できるサービスは多岐にわたります。
お子さまの成長に不安を感じ、「もしかしたら療育が必要なのかもしれない」と心を痛めているお母さんへ。毎日、お子さまの様子を一番近くで見ているお母さんだからこそ抱えるそのお気持ち、本当によく分かります。
「もしかして、私の育て方が悪かったのかしら?」 「この子の将来はどうなってしまうんだろう…」
そんなふうに、ご自身を責めたり、未来に不安を感じたりしていませんか? 大丈夫です。決してあなただけのせいではありませんし、一人で抱え込む必要もありません。
1. 児童発達支援
未就学のお子さまが対象のサービスです。専門の施設に通い、集団活動や個別活動を通して、日常生活での基本的な動作、コミュニケーション、社会性などを育む支援を受けます。遊びを通して楽しく学べるようなプログラムが中心です。
2. 放課後等デイサービス
小学生から高校生までのお子さまが対象のサービスです。学校の授業終了後や長期休暇中に利用し、集団での活動や、学習支援、SST(ソーシャルスキルトレーニング)などを通して、社会性や自立心を育みます。
3. 訪問支援
専門家がご家庭を訪問し、お子さまの発達支援を行うサービスです。家庭での具体的な関わり方や、日常生活での困りごとに対するアドバイスなど、より個別のニーズに合わせた支援が受けられます。
4. 医療型児童発達支援
重い心身の障害を持つお子さまに対し、医療と療育を一体的に提供するサービスです。
これらのサービスは、お子さまの成長段階や特性に応じて組み合わせて利用することも可能です。利用料は、先ほど触れた通所受給者証があれば、原則として費用の1割を負担するだけです(所得に応じて上限額が設定されています)。経済的な心配を抱えずに、必要な支援を受けられるようになっています。
ママ一人で抱え込まないでください
お子さまの発達に不安を感じた時、お母さん一人で悩む必要は全くありません。 「まだ小さいから様子を見よう」「もう少し大きくなったら治るかも」と、時間ばかりが過ぎてしまうこともあります。
もちろん、お子さまの成長には個人差がありますが、もし少しでも気になることがあれば、早めに専門機関に相談することが、お子さまの未来の可能性を広げる大切な一歩になります。
ファイナンシャルプランナーとしての視点からも、療育にかかる費用面での心配は、国や自治体の手厚い支援制度によって大きく軽減されることをお伝えしたいです。
お子さまの「今」を大切に、そして「未来」を共に考え、安心して頼れる専門家や制度がたくさんあります。どうか、その一歩を踏み出す勇気を持ってください。私たち専門家も、お母さんたちとそのお子さまの笑顔を心から応援しています。
もし、子育てに関する家計のご相談や、将来に向けた教育資金のご準備について不安なことがあれば、いつでもご相談ください。
大阪でFP相談ならwith my fp