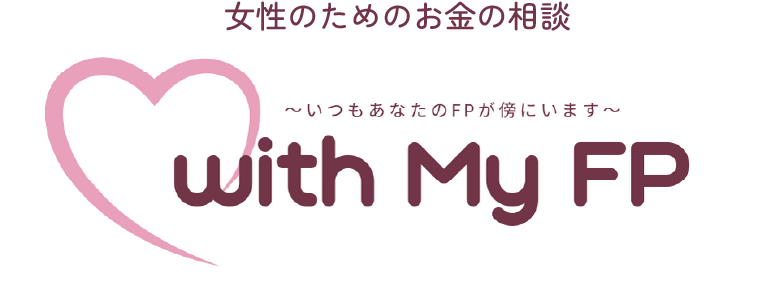家計
自分らしく自立するための「お金」との向き合い方

長い年末年始の連休はどうでしたか?(そうでない方もいらっしゃるとは思いますが)
年も明けて、日常に戻りつつありますでしょうか?
2025年も継続してコラムをお届けできるようにがんばります!
今回は、「経済的な自立」についてお届けします 🙂
自立とは「経済的な安心感」を持つこと
自立というと「仕事を持ち、自分の力で生活する」というイメージが強いですが、それだけではありません。大切なのは、自分にとって心地よいライフスタイルを選び、それを経済的に支えることです。
収入があっても、「何となく貯金しているけれど将来が不安」「資産運用は難しそうで手をつけていない」という声をよく耳にします。自立とは、こうしたお金の悩みを軽減し、安心して人生を楽しむことでもあります。
自分の「価値観」を知ることが第一歩
金融リテラシーを高める前に、自分がどのような生き方をしたいのかを明確にすることが重要です。例えば、
- 旅行や趣味を楽しむ人生
- 将来のためにコツコツ資産を増やす人生
- 家族やパートナーと安定した生活を築く人生
価値観が分かれば、それに見合った「お金の使い方」「貯め方」「増やし方」が見えてきます。
「知識」を味方につける
お金に関する知識は、思った以上にシンプルです。例えば、
- 家計管理:収入と支出のバランスを見直す
- 貯蓄と投資:短期と長期の目標を立てて、それぞれに合った方法でお金を育てる
- 保険や年金:将来のリスクに備える
まずは、無理のない範囲で家計簿アプリを使ったり、ネットや書籍で投資の基礎を学んだりしてみましょう。
小さな一歩を積み重ねる
自立への道のりは、急がなくても大丈夫です。毎月1万円の積立投資でも、5年後・10年後には大きな資産になります。
「お金は苦手」と思わず、小さなことから始めてみましょう。わずかな知識と行動が、未来の安心感につながります。
自分らしい人生を楽しむために
「お金」はツールです。お金に振り回されるのではなく、自分の価値観に合ったお金の使い方ができれば、より充実した人生が送れます。
自分らしく、自立するために、少しずつ「お金と向き合う習慣」を身につけていきましょう。
あなたの未来が、より輝くものになりますように。
大阪でFP相談ならwith my fp
年末年始休業のお知らせ
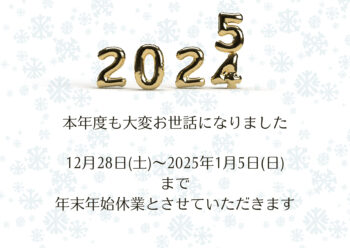
拝啓 師走の候、時下益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。 本年は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
2024年12月28日(土)より2025年1月5日(日)まで年末年始休業とさせて頂きます。
御迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。2024/12/23
今月の家計診断 ~Sさんご一家~

FP塩見です!今回は、家計診断を行ったご家族様の事例をご紹介しますね★
家族構成:・夫 45才 ・妻 40才 ・子供 14才 男性 中学校2年
手取り収入: ・夫の収入: 30万円 +(年2回 ボーナス合計100万円) ・妻の収入: 15万円
支出: ・住居費: 15万円 (大阪郊外)
・食費: 10万円(外食2万円を含む)
・被服費: 3万円 ・水道光熱費: 2万円
・自動車の維持費: 5万円(ローン、ガソリン代)
・旅行の積立て: 2万円
・生命保険: 5万円
・医療保険: 2万円
・教育費(塾): 4万円
・雑費: 3万円
・貯金: 2万円
財産:
・貯金: 100万円
・ローン残高: 車200万円、自宅3000万円
・株式などの他の資産: なし
総合的な評価
こちらの家計の状況は、収入に対して支出が比較的高く、貯金や投資、将来のための準備に関しては少し不十分です。
特に、生命保険や医療保険の支出が高く、家計全体のバランスを圧迫しています。
次に、具体的に改善すべきポイントを挙げていきます。

1. 収入の改善
夫婦合わせて月収45万円(ボーナス込みで年収540万円)という金額は、大阪郊外で生活するには悪くない水準ですが、将来の目標を考えると収入の増加は必要です。
-
夫の収入増加: 夫の収入の30万円は、今後昇給や転職を通じて増やす余地があります。転職の可能性があれば、市場価値に見合った給与を得るチャンスがあるかもしれません。また、副収入を得る手段(フリーランスや副業)を考えることも一つの手です。
-
妻の収入増加: 妻の収入が15万円ですが、パートタイムの時間を増やすか、スキルアップに投資してフルタイムに戻ることで、収入を増やせる可能性があります。今後の家計改善には、この増収が大きな影響を与えるでしょう。
2. 支出の見直し
現状の支出がやや高く、収入に対して不安定なバランスになっています。特に以下の項目において削減可能な部分があります。
住居費
住居費が15万円となっていますが、これは支出全体の中でもかなりの割合を占めています。現状、住居費は家計を圧迫しており、今後の収入増加がなければ、このままでは目標の達成が難しいです。
- 住居費の削減: もし家のローンを再検討できるのであれば、借り換えや、家の売却を考えるのも一つの選択肢です。特に子供が大学に進学するタイミングで、住居の見直しを行うことをお勧めします。
食費
食費が月10万円と高額ですが、外食費が含まれていることが影響しています。
- 食費の削減: 外食を減らし、家庭での食事を中心にすることで、食費は大幅に削減できます。月5万円程度に抑えられるはずです。
被服費
被服費が月3万円ですが、これは一時的に見直す余地があります。
- 被服費の削減: 一時的に被服の購入を控えることで、節約が可能です。月1〜2万円に減らすことが可能でしょう。
旅行の積立て
年1回の旅行は楽しみですが、現状の家計では旅行積立ての額を減らす必要があります。
- 旅行費用の見直し: 毎月2万円の積立てを見直し、1万円に減額することで、年間で12万円の節約になります。旅行は予算内で楽しむ方法を考えましょう。
生命保険・医療保険
生命保険と医療保険の合計が月7万円となっています。これは高額であり、保障内容を見直す余地があります。
- 保険の見直し: 現在加入している保険が過剰な場合は、見直しを行い、必要最低限の保障に絞ることをお勧めします。月3万円程度に削減できる可能性があります。
教育費
教育費(習い事)が月4万円ですが、これは見直し可能です。
- 教育費の削減: 必要でない習い事や活動を見直し、月2万円に抑えることが可能です。
自動車維持費
自動車の維持費が月5万円となっていますが、車が1台のみであれば、維持費の見直しも検討する余地があります。
- 自動車維持費の削減: 車のローンを完済してからの維持費削減を意識し、無駄な支出を減らすことが可能です。また、車の使用頻度を減らし、ガソリン代や駐車場代の節約を目指します。
3. 貯金・投資計画
現状、貯金が100万円ありますが、急な支出に備えるために、まずは生活費の3〜6ヶ月分を目標に貯金を増やす必要があります。
-
短期的な貯金計画: 食費や被服費、旅行費などの見直しで生じた余剰金を、貯金に回すべきです。月々2万円の貯金を3万円に増やし、年内に貯金を150万円に増やすことを目標にしましょう。
-
長期的な投資計画: 株式などの投資は全く行っていないため、投資を始めるべきです。積立型の投資信託を月1万円〜2万円程度で始め、将来の老後資金や子供の教育資金に備えることが重要です。リスク分散を意識し、長期的な視点で投資を進めていってほしいです。
4. 退職計画
老後のための準備が不足しています。夫が45歳で、退職を迎えるまで25年程度ありますが、その間に計画的に老後資金を準備する必要があります。
- 退職後の資金準備: 老後資金は最低でも3000万円以上が目標とされています。そのためには、早い段階から投資信託などを通じて資産を増やしていく必要があります。毎月の貯金のうち、1〜2万円を老後資金に回し、残りを教育資金や生活費の見直しで補うことを検討します。
5. その他必要な事項
・教育費: 高校は私立を考えているとのことですが、その費用が年間100万円〜150万円程度となることを考えると、早急に教育資金の準備が必要です。毎月1万円程度の積立を行い、子供の大学進学資金も含めて準備を進めます。
アドバイス結果
現状のままでは目標を達成するのは難しいため、収入の増加と支出の大幅な見直しが必須です。特に、旅行費用、被服費、生命保険などの支出の削減、投資を始めることで、将来に向けた資産形成を早急に行っていった方が良いです。また、教育資金や老後資金の準備も重要となってきます。
という結果となりました!!
私もやってみたい!という方はお気軽に連絡してくださいね。
大阪でFP相談ならwith my fp
あなたのライフプラン作成しませんか??
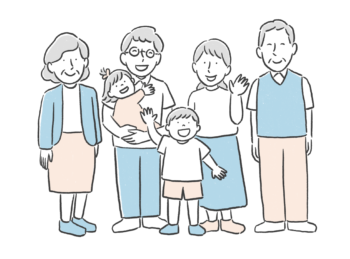
ライフプランとは・・・将来的に起きる可能性のあるライフイベントを想定した計画のことです。
ライフプランを描いておくことで、教育費や住宅の購入費、老後の資金といった大きな支出に備えられます。
主なライフイベント
ライフイベントとは、人生において、将来的に起こりうる出来事のことです。主なライフイベントには、以下のような出来事が挙げられます。
・一人暮らし
・就職、転職
・結婚
・出産
・住宅の購入
・車の購入
・子どもの進学
・定年退職 など
人によって異なりますが、自分の人生に起こりうるライフイベントを事前に考えておくことで、貯蓄などに対するモチベーションも上がるかも?!
人生の3大支出とは?
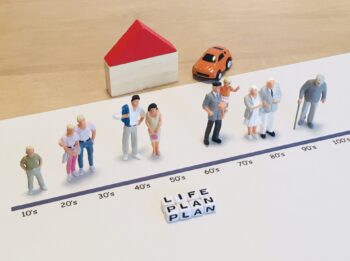
人生の中には大きな出費があります。その中でも教育・住宅・老後については1.5億円ほど使うと言われています。
教育費
子供にかかる費用は入学金や授業料、さらには塾代や習い事などがありますよね。
子供1人あたり、約1043万円(幼稚園~大学まで。文部科学省の調査結果より試算)と言われています。
住宅費
家の購入をする場合は、その後の修繕費・住宅ローンに係る費用・固定資産税などがかかります。
新築の注文住宅を購入した場合、全国平均で約5,500万円ほどの費用がかかると言われています。
老後費用
老後にかかる生活費、趣味のための費用、入院・通院費などを賄うための資金を指します。
総務省の「令和4年度 家計調査年報(家計収支編)」で報告されている、65歳以上の無職世帯における消費支出は以下のとおりです。
- ・65歳以上の夫婦のみの無職世帯:約24万円
- ・65歳以上の単身無職世帯:約14.5万円
この調査結果を踏まえて、65歳から85歳までに必要な生活費を算出すると、夫婦世帯では約5,760万円、単身世帯では、約3,480万円となります。なお、これは消費支出から算出したものであり、いわば必要最低限ともいえる費用です。そのため、ゆとりのある生活を送りたい場合はさらに資金が必要ですよね
ライフプランを描くメリットとは?
①大きな出費に備えられる
②家計の見直しができる
③万一に備えられる
もはや備えあれば憂いなし。
ライフプランを作成しようと思うと、手間と時間はかかりますが・・・
そんなときは、withMyFPへぜひご相談にきてください。
しっかりとあなたの人生の希望を反映させた、ライフプランを一緒につくりましょう!
大阪でFP相談ならwith my fp
103万円の壁問題!ついに動く??

お久しぶりのコラム投稿になってしまいました。
衆議院解散総選挙後テレビでは、【103万円の壁】が話題ですね。
パートやアルバイトで働いている方は、年末に差し掛かるこの時期、今年は大丈夫?と気にされている方が多いのではないでしょうか?

そもそも【103万円の壁】って??
103万円の壁とは、給与収入が年103万円を超えると、自分のバイト代やパート代などに所得税が課税され始める年収額を指します。
学生やフリーターなど家族の扶養に入っている人は、年収103万円を超えると扶養を外れ、親などの扶養者の所得税と住民税が増える年収額でもあります。
税金は、課税対象の所得≒収入を1円でも超えると、税金が課税されたり、扶養から外れるので、対象になりそうな人は注意が必要な額なんです。
103万円を超えたら・・・どうなるの??

ずばり。自分に所得税が課税され始めます。
そして・・・扶養してもらってる方は、税制上に扶養から外れるため扶養控除額に対する所得税と住民税が扶養者にも課税されます。
とくに学生のアルバイトの方で、親の扶養から気づいたら外れてしまっていた!!というのはよくある話ですね。
いつからいつまでの分が対象になるの??
【103万円の壁】は1月~12月の総額
所得税や扶養控除の対象となる103万円は、その年の1月から12月の1年間の収入総額です。
この総額は、手取りではなく、税金や社会保険料を引かれる前の給与で、掛け持ちや途中で辞めたバイトやパート代も合算します。
ちなみに、この103万円の中に、交通費は含めません。
超えたらいくら払う??
バイトやパートの年収が103万円を超えた場合、超えた分に所得税がかかります。所得税は超えた額に税率を掛けて計算します。
また、住民税は均等割と所得割があり、均等割は93~97万円(地域による)を超えると3000円~5000円程度かかり、
所得割は100万円までは非課税ですが、100万円を超えると課税されます。課税額は、給与から基礎控除と給与所得控除の合計98万円を引いた残りに、税率を掛けて算出します。
【年収110万円の場合、支払う所得税・住民税】
■所得税 3,500円
■住民税 12,000円+3,000円~5,000円(地域によって異なる)=15,000円~17,000円
ご参考まで★
他にも【壁】は存在します!
最低賃金が上がり、ますます働き方を考える事が重要な時代になってきてます。
政治家のみなさんには、国民に寄り添った改正を期待したいところですよね!!
詳しく知りたい!という方は、いつでもご相談にきてくださいね!
大阪でFP相談ならwith my fp
【FP 大阪】年金定期便の見方知ってる??

お誕生日月に毎年発行されている、「ねんきん定期便」はキチンとチェックしてますか??
そもそも「ねんきん定期便」って??
「ねんきん定期便」は、年金制度に対する国民の信頼を向上させることを目的として、国民年金、厚生年金保険に加入している人宛てに日本年金機構が毎年郵送するものです。これを見ることで、年金の見込み額、年金制度の加入記録などを確認できます。
ねんきん定期便は誕生月の2カ月前に作成され、毎年誕生月にはがきで届きます。また、35歳、45歳、59歳の節目年齢には、封書版のねんきん定期便が郵送されます。
近年はハガキではなく、電子版のねんきん定期便をインターネットでダウンロードすることも選べるようになりました。
数年に1度、封筒でくるけど??
はがき版のねんきん定期便では「最近の月別状況」として直近13カ月の記録を確認できます。これに対し、封書版では「これまでの年金加入履歴(加入してきた制度ごとの資格取得・喪失の履歴)」と「これまでの厚生年金保険における標準報酬月額などの月別状況(全期間)」が記載されます。
はがき版よりも詳細な加入期間の情報が確認できますので、以下のポイントをチェックすることをおすすめします。
<封書版のねんきん定期便で確認したいポイント>
1.年金加入履歴に漏れや誤りがないこと(国民年金保険料を納付していた時期や、就職・離職の時期、勤務先名などの記録が自分の記憶と一致していること)を確認しましょう
2.全期間の月別状況では、給与と賞与の推移が記憶と大体一致していることを確認しましょう
公的年金シュミレーターを活用してみよう
50歳未満の方に届くねんきん定期便には、残念ながら将来もらえる年金の金額は記載されていません。
2022年度からねんきん定期便に「年金見込額試算用二次元バーコード」が記載されるようになりました。スマホやタブレットなどのカメラでこの二次元バーコードを読み取ると、厚生労働省の「公的年金シミュレーター」が起動します。生年月日を入力して「試算する」を選択だけで、将来もらえる年金見込み額がグラフで表示されます。
また、サイト内のスライドバーを操作して左右に動かすと、年金をもらいはじめる時期などを変更した場合の試算もすぐにできます。利用は無料で、ID・パスワードなども不要。手軽に使えますので、ぜひ試してみてください。
老後の年金はいくらもらえるのか、年金だけで生活できるのかなど、将来のことが気になっている方は多いでしょう。それであれば、まずはねんきん定期便の確認から。ポイントを押さえてチェックし、将来の年金額を知っておきましょう。
大阪でFP相談ならwith my fp
【FP 大阪】定額減税 わかりやすく解説

6月から始まる所得税と住民税の定額減税。岸田文雄政権の目玉政策ですが、制度はちょっと複雑のようです。
仕組みや効果を整理してみましょう。
国民1人あたり 4万円減税
定額減税により、
・2024 (令和6)年分の所得税額から3万円×(本人+扶養親族数)
・2024 (令和6)年度分の個人住民税所得割額から1万円×(本人+扶養親族数)
の減税がされますが、減税しきれない額があるため、これに加えて、個人住民税が課されている市区町村から、調整給付がなされる見込みがあります。
例えば家族4人の場合、4万円×4人=16万円分の税金が減るという事ですね。
しかし、上記のケースや扶養家族の人数が多い場合、年間の納税額から、減税額全てを差し引けないというケースが想定されます。
この場合、給付金という形で考えているという事です。
給付の場合はナント1万円単位。例えば減税がしきれない額が11,000円だった場合でも20,000円の給付となる予定です。
これは公平と言えるのか?と少し疑問が残る所ですよね。
なぜこのタイミングで減税が必要なのか?
政府は物価高に苦しむ家計を支援し、物価と賃金がともに上がる好循環を作り出すことを目指しています。
給与明細に減税額を明記するよう企業に義務づけ、国民に手取りが増えたことを実感してもらおうとしています。
電気代やガス代の補助金も打ち切られるタイミングで減税を強調したかったのかもしれないですね。
例外的な手続きが必要な場合もある
基本的に給与所得者は納税者本人の手続きは不要ですが、例外的に以下の場合は手続きが必要になります。
- ★令和 6 年分の所得金額(合計)1,805 万円を超える場合
- ★令和 6 年 6 月以降に「扶養控除等申告書」・「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の内容にに変更があった場合。(例:結婚・出産・扶養していた子供の就職・扶養配偶者が扶養から抜けたなど)
念のため、扶養親族に当てはまる人を確認しておきましょう。
令和 6 年 12 月 31 日の現況で、以下の四つすべてに当てはまる人が定額減税の対象扶養親族に当たります。
- ★配偶者以外の親族(6 親等血内の血族・3 親等内の姻族)
- ★納税者と生計を 1 つにしていること
- ★年間の合計所得金額が 48 万円以下であること
- ★青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いをうけていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
- 6 月以降に、この四つの条件から外れるご家族がいる場合は、年末調整または確定申告で手続きが必要になります。
みんなが気になる【あの制度】との兼ね合いは??
①住宅ローン減税に影響はあるのか??
結論から言いうと、定額減税が導入されても住宅ローン減税には基本的に影響はありません。
定額減税分の所得税がもし 2026 年 12 月までに減税できなかった場合は、その分 1 万円単位の給付金で受け取れます。
②ふるさと納税は??
ふるさと納税には控除になる寄付金に限度額がありますので、その基準が変わってしまうのではないかと心配されると思います。
ですが、ふるさと納税も気にしなくても大丈夫です!
ふるさと納税の控除寄付金の上限は、定額減税を行う前の金額で計算すると決まっているからです。
③配偶者の所得
- まず、扶養配偶者かどうかを判定するのは 2024 年の 12 月 31 日です。
- この時点において、年間の合計所得金額が 48 万円(給与所得だけの時は 103 万円)以下の人を言います。
- 2024 年 12 月 31 日時点で、配偶者の収入がこの金額を超えていた場合は、年末調整や確定申告が必要になります。一度控除された税金を返す必要があります。
- その場合は扶養を抜けた配偶者自身の減税という形になります(返す金額と配偶者が納税者本人として受け取る金額は必ずしも一致しません)
配偶者が今収入がないけどフリーランスを目指して頑張っている場合など、年末調整が必要になるかもしれないと心に留めておいてくださいね。
大阪でFP相談ならwith my fp
【FP 大阪】40代子育てママが取り入れやすい節約術!!

物価がますます上昇していますよね!
そしてあまりお給料が上がった気がしない・・・という方は多いのではないでしょうか?
40代の主婦が日常生活に取り入れやすい節約術
食費の節約には食材の無駄を減らすことが大切です。
食材を無駄なく使い切るために、週に一度のメニュープランニングを行い、買い物リストを作成することが効果的。
お惣菜や外食を減らし、自炊を心がけることで家計を助けることができます。
また、光熱費の節約には、電気やガスの使用を見直すことが重要です。電気製品の無駄な待機を減らし、断捨離を行うことで無駄な光熱費を節約できます。
定期的な家計簿のチェックを行う
支出を把握することができます。家計簿をつけることで、毎月の支出や収入を把握しやすくなり、
無駄な支出を見つけることができます。
そして将来の計画を立てやすくなります。家計簿をつけることで、将来の大きな支出や貯金の目標を立てやすくなります。
さらに、節約意識が高まります。家計簿をつけることで、自分の支出に対する意識が高まり、無駄な支出を減らすことができます。
貯金は大きなモチベーションになります
貯金することで将来の安定や自由を手に入れることができるため、多くの人にとって貯金は非常に重要な活動です。
また、貯金することで将来の目標や夢を実現するための資金を準備することもできます。
貯金は健全な財政管理の一環として、将来に向けての計画を立てる上で重要な役割を果たします。
とは言うものの、なかなか実行するのが苦手という方も多いのでは??
そんな方は一緒に家計診断をしましょ☆
大阪でFP相談ならwith my fp
【FP 大阪】2025年問題とは??

2025年問題とは「団塊世代の全員が後期高齢者となり、超高齢社会を迎えることで生じるさまざまな影響」のことを指し、さまざまな業界へ多大な影響を与えることが懸念されています。
2025年問題で予想される影響は?
◎社会への影響
- 社会保障費の増大による現役世代への負担増加
- 経営難でない企業の廃業による経済縮小の加速
- 介護や医療の人材不足により体制維持が困難に
◎企業への影響
- さまざまな業界で深刻な人材不足
- 後継者不足による黒字廃業
- 既存システム維持の困難化により企業・業界の成長の妨げに
2025年を目前に控えた今、対策を行わなければ、将来的に企業の競争力が低下する可能性が高くなるでしょう。なぜなら、2025年問題は過渡期的な現象で、ピークはさらにその先にあるからです。
ビジネスケアラーが増大
ビジネスケアラーとは、働きながら家族の介護を行う人のことです。高齢者の増加にともない、今後はビジネスケアラーが急増することが見込まれています。
経済産業省の資料によると、2030年には家族介護者の約4割がビジネスケアラーになると試算されています。仕事と介護の両立困難による労働生産性損失はきわめて大きく、2030年には損失額が約9.1兆円にのぼる見込みです。
従業員の「介護離職」を防ぎ、安定した労働力を確保するためには、職場環境や社内制度の整備が欠かせません。短時間勤務や在宅勤務の導入など、従業員一人ひとりの状況に合わせた働き方を整備することが大切です。
2025年問題に向けて私たちができること
社会保障制度を維持し、日本経済の衰退を防ぐためにも、一人一人の健康寿命を延ばすことも重要と言えます。
健康寿命とは、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」のこと。
厚生労働省は2019年に、2016年に男性72.14歳、女性74.79歳だった健康寿命を、2040 年までに男女ともに3年以上延伸し、男性75.14歳以上、女性77.79歳以上を目指す「健康寿命延伸プラン」を策定しました。
スポーツ庁との連携強化、地域における健康づくりの促進など、さまざまな取り組みが行われていますが、何よりも私たち一人一人が「少しでも長く、健康であるために」という意識のもとに生活をしなければ、健康寿命を延ばすことは難しいでしょう。
年齢を重ねても健康で過ごすために、今のうちから健康的な生活を習慣づけ、趣味が合う仲間とスポーツを楽しんだり(別タブで開く)、地域のお祭りなどのイベントに参加したり、楽しみながら人とつながり続けることが、私たちにできる最善策かもしれません。
大阪でFP相談ならwith my fp
【FP 大阪】主婦(主夫)でも取れる!FP資格の魅力!!
「何か資格を取ってみたいけど、どの資格が良いのか分からない・・・」
こんな風にお悩みの主婦の方はいらっしゃいませんか?
この記事では主婦の方に特にオススメの「ファイナンシャルプランナー」という資格についてご紹介します!
魅力いっぱいのファイナンシャルプランナーを取得して、あなたの生活を今以上に素敵にしちゃいましょう!
https://youtube.com/shorts/gtIE0RMPe10?si=9YgsDdq_y9Kxjgrw
大阪でFP相談ならwith my fp
悩む前にまずはご相談ください。
誠心誠意お応えいたします。

3営業日以内にご返信・24時間/365日受付
生活のこと、お金のことなどお気軽に
お問い合わせください。
資料もご用意しておりますのでご希望の方は
記載お願いします。
相談予約フォーム
お電話でもまずはお気軽にご連絡ください。
ご相談の概要をお聞きした上で、ご相談日を決めさせていただきます。